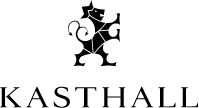1931年、数寄屋建築の名工、中村外二が京都に興した中村外二工務店。京都迎賓館をはじめ、美山荘や俵屋旅館といった名旅館、高台寺 和久傳や菊乃井などの名料亭を手掛け、国内外にその名が知られています。中村外二工務店が手掛ける数寄屋建築に調和するしつらえを提案するために1984年に立ち上げたのが興石。同社では、指物の制作をはじめ、高品質な北欧家具や照明、食器などの輸入と販売を行っています。
京都・北大路大通りにあるショールームには、美しい北欧家具と共にカスタールのラグも並んでいます。今回は、興石で家具の買い付けとコーディネートに携わる伊久 茜さんにお話を伺い、カスタールが⽇本の建築に馴染む理由を伺いました。
凛とした空気感をもつ
中村外二の数寄屋建築と北欧家具
–– 興石では数寄屋建築に調和する家具として北欧家具を提案されています。どのような理由からでしょうか?
伊久 茜さん(以下、伊久) 興石は中村外二工務店の二代目・中村義明が創業しました。きっかけは、中村外二工務店が1972年に携わったロックフェラー邸。このプロジェクトには世界のさまざま分野のプロフェッショナルが集められ、吉村順三さんが設計、ジョージ・ナカシマさんが家具、中村外二工務店が施工を担当しました。2代目はこの経験を経て「家具についてもっと学び、自分たちが手掛ける建物に合う家具を追求したい」という思いに駆られたそうです。

京都・北大路大通りにある興石のショールーム。デンマークを中心とした北欧のヴィンテージ、現行品がセレクトされている。いずれも中村外二工務店が手掛ける数寄屋建築に調和する、クラフトマンシップあふれる美しい家具だ
中村外二工務店が手掛ける数寄屋建築は繊細です。それに合う家具として2代目がたどり着いたのが、木の温もりとクラフトマンシップあふれる北欧の家具。なかでも曲線美と柔らかな雰囲気をもつデンマークのヴィンテージ家具でした。
––当時は輸入家具というとイタリアなど西欧のものが主流で、北欧のものは多くはなかったのでは?
伊久 その頃は日本に北欧家具メーカーの輸入代理店がなく、現行商品も弊社で直輸入していました。ヴィンテージ家具に関しては、当時のマネージャーがデンマーク人で古いものを入手するネットワークがあり、買い付けがしやすかったんです。現在はヴィンテージ品はデンマークで主に買い付けをし、現行品はデンマークのほか、スウェーデンやフィンランドの商品も取り扱っています。


興石には家具部のほか指物部もある。釘などの接合部材を使わず、指し合わせて制作する照明やインテリア小物も手掛けている
–– セレクトの基準はありますか?
伊久 家具を選ぶ基準は“2代目の目”です。それが明確に何なのかを表現するのはむずかしいですね。本人に尋ねても「わしがいいと思ったからや」という返答でしたから(笑)。ひとつだけ言えるのは、家具としての機能性や構造強度などを度外視した、彼にとって美しいかという絶対評価だったということです。たとえば、ハンス J. ウェグナーの家具のように隙がないほど機能的で美しいデザインよりも、フィン・ユールの家具のように色気を感じさせるものや、コーア・クリントの家具のように独特の凛とした佇まいのものを好みました。
ただ、彼はうんちくが好きではなかったので、レアで高い値がつくものや著名デザイナーが手掛けたデザインだからといって買い付けたりはしませんでした。私がいくら情報を加えても「で、ほんまにええと思ってんの?」と(笑)。


上/興石のショールームには、美しい北欧家具に並んでカスタールのラグも展示されている 下/興石の家具部を担当する伊久 茜さん(右)と河児美紗さん(左)
–– 研ぎ澄まされた感性と審美眼をもった方だったのですね。2022年に逝去され、現在はその意思を受け継ぎ、伊久さんが“2代目の目”を読み解いてバイイングをされていると。
伊久 興石に入社して約20年、徹底して叩き込まれましたから(笑)。彼は学生時代に建築を学ばなかった分、独学で勉強したり、さまざまな人と交流を深めたりするなかで独自の嗅覚を養っていました。彼が好んだフィン・ユールや李朝家具などが後々価値が上がっていくのを見て、目利きってこういうことなんだと感じましたね。今も買い付けで悩むと「この家具、親方は好きかな?」と考えます。
カスタールのラグが京都の町家建築になじむ
–– つまり興石では、中村外二の数寄屋建築とデンマークのヴィンテージ家具に調和するものとして、カスタールのラグをご紹介くださっていると。
伊久 北欧ヴィンテージのように重厚な家具の場合、素材感やクオリティの点でそれに負けない存在感のラグを敷きたいもの。同じラグでいうと緞通も候補として考えられますが、和のテイストがやや強くなります。日本家屋と北欧ヴィンテージ家具に合わせるなら、カスタールがぴったりだと私は思っています。


上/2020年3月に開業した「THE HIRAMATSU 京都」。京町家の歴史的価値を活かし再生したホテルで上質な時を提供するとともに、地域の歴史と文化を継承し、町の活性化に貢献することを目指した
カスタールのラグは遊び心をもちながらも落ち着きがあり、普遍的な空気を纏っています。世の中にはデザインだけを前面に押し出してくる製品もありますが、カスタールのラグは奇をてらっておらず、主張しすぎない。少し尖ったデザインも過剰でなく、知的。一方で、目に訴えかけてくる強さもある。興石が買い付ける家具との共通点でもあると思います。
–– カスタールのものづくりを理解してくださっていて嬉しいです。興石が家具のコーディネートに携わられた京都の2軒の宿にもカスタールのラグを採用いただいていますね。

「デラックスプレミア」はダイニングと旅館の「広縁」のようなサロンが配されている。ダイニングの下は厚み3.5㎜でフラットな「Harper」をコーディネート
伊久 はい。ひとつは「THE HIRAMATSU 京都」。室町通りに面する築120年を超える町家を保存、増築することでホテルとして再生するプロジェクトです。中村外二工務店が監修し、興石は客室から共用部まで施設全体の家具を監修させていただきました。そのうち25の客室にカスタールのラグをコーディネートしています。客室は建築家の金 澤富さんが設計され、障子戸や格子の間仕切り、和紙の壁紙、無垢のフローリングと京都の歴史と風情を感じさせるインテリアとなっています。
ここに、J.L.モラーやカッシーナ・イクスシーの家具などをお選びいただきました。ラグもまた、この上質な空間に調和するものが必要でした。加えて、客室のレイアウトに合わせたさまざまなサイズのラグを、客室ごとにできるだけデザインを変えたいという要望もありました。総合的に見てカスタールしかないと、ご提案しました。


写真左は「デラックスプレミア」のダイニングスペース。写真右は「スペーリア」のソファエリア。どちらも「Harper」だが、部屋ごとに異なるカラーとし雰囲気を変えている
–– 「THE HIRAMATSU 京都」では「Harper」と「Marocco」を選ばれています。その理由を教えてください。
伊久 前提として、メンテナンスがしやすいように毛足の長いものでなく、糸を織り上げたウーブンラグを選びました。ダイニングセットの下に敷くラグは、万が一食べこぼしがあってもメンテナンスがしやすいように、厚さ3.5㎜と薄手でフラットな「Harper」に。ニュートラルな色から明るい色までカラーバリエーションの幅が広いので部屋ごとに雰囲気を変えられると思いました。


「デラックス」の障子の上には、呉服商出身の尾形光琳による光琳大波文様が描かれた異素材が貼られており、京町家とのつながりを感じさせる。アームチェアはインテリアデザイナーの植木莞爾さんがデザインしたカッシーナ・イクスシーの「TANT-TANT」。その下にカスタールのラグ「Marocco」をコーディネートした
「Marocco」はこの連続したパターンが美しく、いつかお客さまにご提案したいと考えていたデザインのひとつでした。立体感のある糸を織り上げているのでふっくらとしていてリッチな雰囲気なので、アームチェアの下に敷けばゆったりと寛いでいただけるのではないかと思いましたね。
–– 「Marocco」パターンは、北アフリカの文化が発想源となっているのですが、こんなにも和のインテリアに調和するのですね。カスタールのラグをコーディネートしてくださったもう一軒の宿「祇園の宿杏花」も同様に、和と洋のバランスが絶妙です。

2021年3月、祇園に開業した「祇園の宿杏花」は、かつてお茶屋だった京町家の趣を残しながら改修した宿泊施設
伊久 祇園にある「祇園の宿杏花」は大正時代建造のお茶屋を改修した宿泊施設で、家具の監修を興石が担当しました。畳敷きの和室もあり、天童木工の座椅子と座卓のほか、フィン・ユールのアームチェアとオットマンなどをコーディネートしました。畳の上に家具を置く場合、畳を傷めないようにベタ脚タイプを選ぶのが一般的ですが、選択肢が少ないんです。それにソファやテーブルなどの西洋の家具を畳の上に直に置くのは違和感がある。だから家具の下にラグを敷くのは必須と考えました。その延長でベッドルームやリビングにもラグを敷くことをご提案しました。



上/「祇園の宿杏花」は「京からかみ」を各所にしつらえたり、銀鼠や臙脂といった和の伝統色を壁のアクセントカラーとして用いたり、一部をフローリング貼りにするなど現代的な要素を取り入れた空間となっている 左下/町家の趣を生かして改修されたエントランス 右下/「和室デラックスダブル」は畳敷きの和室のほか、フィン・ユールのソファとテーブルが配されたリビングもあり、家族や仲間とゆったり使える仕様。ソファの下に敷いたカスタールのラグ「Muse」がインテリアにアクセントと統一感をもたらしている
–– 「祇園の宿杏花」ではウーブンラグ「Muse」と、「THE HIRAMATSU 京都」でも採用した「Harper」をコーディネートしています。「Muse」はメダリオンのようなパターンが個性的ですが、これも町家建築によくなじんでいると感じます。
伊久 ラグは「祇園の宿杏花」のオーナー様とお打ち合わせをしながら決めました。「Muse」は織りのパターンがユニークで、ブルーやブラウン、グレーなど多色が用いられています。家具の色合いと同系色とすることでインテリアに統一感をもたせました。


上/「≪臙脂≫和洋室デラックスダブル」のベッドルームは臙脂色の壁面がアクセント 下/窓辺にはフィン・ユールによる一人掛けソファが配された憩いの空間が。カスタールのラグ「Harper」のネイビーとソファのツートーンの張り地の色合わせが美しい
ラグはインテリアにおける“調整役”だと私は思っているんですよ。たとえば今回のように、家具に調和する色または反対色のラグを家具の下に敷くことでインテリアに統一感が生まれる。極端にいうと、家具の色がそろっていなくても、ラグを敷くだけでトータルでまとまりが出るんです。
–– ラグはインテリアをまとめる“機能”があると。家具のバイイングやコーディネートにかかわるインテリアのプロならではの視点ですね。
伊久 私はインテリアにはラグが必須だと考えています。ラグを敷くだけで空間がぐっと引き締まりますから。ラグは後回しになってしまうことも多いのですが、家具と同じタイミングで選ぶと完成度の高いインテリアができると思います。

実は私、自宅でカスタールの「Tekla」を愛用しているんですよ。家具もインテリアも当然大好きですが、日々家具に囲まれていると、買わなくても満足してしまったりもするんです(笑)。でも「Tekla」はひと目見て心を掴まれて、購買意欲に達する魅力がありました。アレルギー持ちですが全然ちくちくしないし、静電気も起こりません。「Tekla」は毛足が長いのですが、掃除機を使って手入れもしていて、オールシーズン快適に使っています。カスタールの素晴らしさを、日々身を持って実感しているんですよ。
〈取材協力〉
THE HIRAMATSU 京都
京都市中京区室町通三条上る 役行者町361
TEL. 075-211-1751
https://www.hiramatsuhotels.com/kyoto
祇園の宿 杏花
京都市東山区大和大路通四条上る二筋目東入末吉町86番地
TEL.075-708-6577
https://gion-kyoka.com

伊久 茜さん
興石 家具部
幼少期に父が所有するインテリア雑誌で「PK22」を見て北欧家具の魅力を知る。大学ではジャーナリズムを学び、卒業後はインテリアの世界へ。2002年に興石に入社。中村外二工務店の2代目・中村義明氏の下で家具の買い付けからコーディネート監修、販売までを担当。飲食店や物販店などの店舗、宿泊施設などを中心に、現代的な和の空間に調和する家具を提案している。 https://kohseki.com

Sotoji Nakamura is known as a master craftsman of sukiya style buildings (a house in the style of a tea-ceremony pavilion). In 1931, he founded the Nakamura Sotoji Komuten in Kyoto, where he worked on the Kyoto State Guest House, famous ryokans such as Miyama-so and Tawaraya Ryokan, and famous restaurants such as Kodaiji Wakuden and Kikunoi. Yoshiaki Nakamura, the second generation, started Kohseki in 1972 after working on the Nelson Rockefeller House to propose interiors that harmonize with sukiya style buildings. The project brought together professionals from various fields around the world, with design by Junzo Yoshimura, one of Japan’s leading architects, furniture by George Nakashima, and construction by Nakamura Sotoji Construction Company. Currently, the company produces fingerware, as well as imports and sells high-quality Scandinavian furniture, lighting, tableware, and other items. Yoshiaki favored vintage Danish furniture with its curvaceous beauty and soft atmosphere. Since Yoshiaki’s death in 2022, Akane Iku has continued to buy with her “Yoshiaki’s eye,” following in his footsteps.
Kohseki believes that Kasthall rugs are in harmony with Sotoji Nakamura’s sukiya style buildings and vintage Danish furniture. Kasthall rugs are playful, yet calm, and have a universal air about them. Kasthall’s rugs are not eccentric, not too assertive, and their slightly pointed designs are intelligent without being excessive. At the same time, they have a strength that appeals to the eye,” says Iku. Kasthall rugs are also used in two inns in Kyoto for which Kohseki coordinated the furniture. “THE HIRAMATSU KYOTO” is a project to preserve a 120-year-old machiya (townhouse) and add on to it to revitalize it as a hotel. Nakamura Sotoji Komuten supervised the project, and Kohseki proposed furniture for the entire facility, from guest rooms to common areas. 25 of the guest rooms are furnished with Kasthall rugs. “Harper” and “Marocco” were selected, and the color was changed for each room. “Gion no yado Kyoka” is an accommodation facility that was renovated to retain the atmosphere of a former tea house. The “Muse” design, with its unique medallion-like pattern, blends well with the machiya architecture.
Akane Iku
Kohseki buyer/coordinator
As a child, she saw “PK22” in her father’s interior design magazine and discovered the appeal of Scandinavian furniture. After studying journalism at university, she entered the field of interior design and joined Kohseki in 2002. Under the supervision of Yoshiaki Nakamura, the second-generation owner of Nakamura Sotoji Komuten, she was in charge of everything from furniture purchasing to coordination supervision and sales. She proposes furniture that harmonizes with modern Japanese spaces, mainly for restaurants, retail stores, and lodging facilities.
https://kohseki.com/
Photographs:Satoshi Shigeta
Text:Kyoko Furuyama(Hi inc.)
Creative Direction:Hi inc.
- HOME
- Why? Kasthall
- – Kasthall meets KYOTO –中村外二と興石が選んだ京町家に合うラグ